事業戦略を果たすための評価制度設計のガイドライン
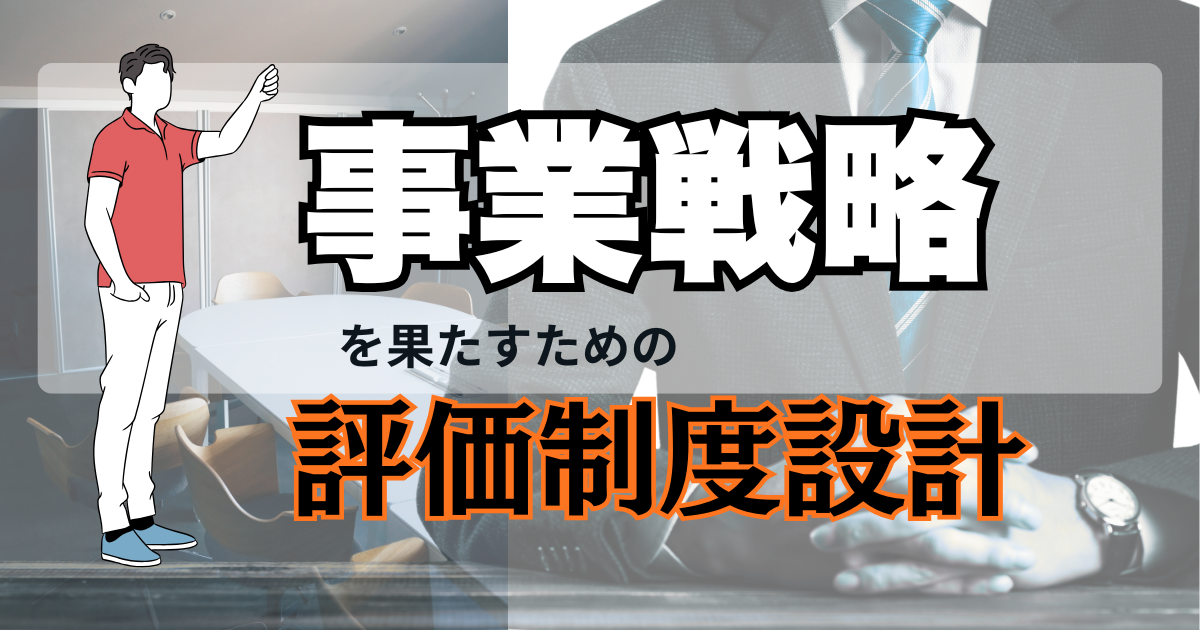
事業戦略を果たすためには大きくわけて2つの要素が必要です。1つ目は、戦略の妥当性。2つ目は戦略通りに従業員が実行してくれるかどうか。戦略が正しくても、思った通りに動いてもらわなければ、それは戦略が正しいのかどうか判断がつきません。本稿では、従業員に戦略に基づいて動いてもらうための方策として、評価制度作成において気を付けるべき点をステップバイステップで案内します。
ステップ1: 事業戦略と評価制度の連携を設計する
- 事業戦略を明確化する
- 企業が達成したい中長期的な目標(例: 売上成長、イノベーション推進、市場シェア拡大など)を具体的に定義します。
- この戦略を達成するために、組織や従業員に求められる具体的な行動や成果を洗い出します。
ここでのポイントは、企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を策定しておくことです。何のためにこの事業をするのかを明文化することで、戦略に一本筋が通ったものになります。MVVとKPIが紐づいているかは、評価項目を設定するうえで、非常に重要な要素となります。紐づいていないと、MVVは絵にかいた餅になりますので、経営者は、その想いを明文化し内外に示していきましょう。
- 評価基準を戦略に基づいて設計する
- 戦略目標に合致するKPI(重要業績評価指標)やKGI(重要目標達成指標)を設定します。
- 個人、チーム、部門ごとに適切な評価項目を設け、定量的・定性的な基準を組み合わせます(例: 売上達成率、プロジェクトの完了率、顧客満足度、創造性など)。
評価項目を設定する際に考慮すべき点があります。部門間で摩擦が起こらない項目にしてみてください。例えば、仮に事務の項目に「書類の不備率を〇%削減する」という項目を設定したとします。ただ、その不備の原因の殆どが、実は営業側が事務側に書類を渡す際に発生する項目の記載に漏れに起因する場合、事務側からすれば、自分の責任範囲の中で解決できない項目になっているかもしれません。評価項目を設定する場合は、免責がおこらないように設定することがポイントです。また、先ほどの例のような場合は、受け渡しの際のルールを設定し、責任の範囲を決めておくと良いでしょう。
- 企業文化や価値観を反映させる
- 評価基準に企業の価値観(例: チームワーク、倫理観、顧客志向など)を組み込むことで、従業員が望ましい行動を理解しやすくします。
定性的な項目を設定する場合には、出来るだけ定義化し、出来た出来ないの基準を決めておきましょう。また、評価に際しての比重も重要です。一般的には、階層が上になるほど定性部分の比重は少なくなっていきます。
ステップ2: 評価プロセスを構築する
- 透明性のある評価プロセスを設計する
- 評価の基準、プロセス、スケジュールを明確にし、全従業員に周知します。
- 評価プロセスにおいて、従業員が自身の目標や役割を正確に理解できるようにします。
大前提として、従業員への説明は必要です。また。社内規定も変更する必要があります。不利益変更になる可能性もあるので、試運転は必ず行い、適正であるかを確認していく必要があります。
- 目標設定(MBO: 目標管理制度)を導入する
- 従業員と上司が協力して具体的な目標を設定し、それが事業戦略と一致していることを確認します。
- SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)基準を用いて目標を設定します。
MBOは1つの例です。企業によって、最適なものは違います。また、環境の変化や、事業フェーズ、さらに事業部毎にも最適なものはあるので、専門家と相談しながら決めていきましょう。
- 定期的なフィードバックを組み込む
- 年1回の評価だけでなく、四半期や月次でのフィードバックセッションを導入し、従業員が進捗を把握できるようにします。
- フィードバックでは、成果だけでなくプロセスや行動についても不足を確認していくと良いでしょう。
上司のフィードバックの仕方が重要です。「どうすれば目標を達成できるか」という観点でフィードバックを行ってください。また、すぐに解決策を教えるのではなく、部下に考えさせることも重要です。考えさせる機会をたくさん与えるためにも週次での確認をお勧めしています。
ステップ3: 評価結果を活用する
- 報酬や昇進に反映する
- 評価結果を基に、給与、ボーナス、昇進、昇格などの意思決定を行います。
- 成果に応じた公平な報酬体系を構築することで、従業員のモチベーションを高めます。
- キャリア開発に役立てる
- 評価結果を基に、従業員ごとにスキルギャップやキャリア目標を特定し、適切な教育・研修プログラムを提供します。
- 将来的なリーダー候補を発掘し、育成計画を立てます。
- 配置転換やタレントマネジメントに活用する
- 評価データを活用して、従業員を適材適所に配置し、組織全体の生産性を向上させます。
- 高パフォーマーを重要なプロジェクトや役割に配置することで、事業戦略の実行力を高めます。
従業員の育成スケジュールを作成しておくと非常に便利です。多くの経営者から「なかなか育たない」という声を聴きますが、私はいつも「そもそもいつまでにどうなってほしいのかをきちんと設定して、従業員に開示していますか?」と問いかけています。従業員がまったく育たないということではなく、思ったスピードで育たないということだと思うのです。それを解消するためにもスケジュールを作成し、また進捗を測る機会を設けることがポイントです。
ステップ4: 評価制度の改善を継続する
- 評価制度の定期的な見直しを実施する
- 事業環境や戦略の変化に応じて、評価基準やプロセスをアップデートします。
- 従業員や管理職からのフィードバックを収集し、改善点を特定します。
- データを活用した分析を行う
- 評価結果を分析し、組織全体のパフォーマンス傾向や課題を特定します。
- 評価データを基に、長期的な人材戦略や組織改革の方向性を決定します。
- 公平性と透明性を維持する
- 評価プロセスにおけるバイアスを防ぐため、第三者のレビューや評価ツールの導入を検討します。(評価に直結させるかは要検討)
- 従業員が評価制度に納得感を持てるよう、運用の透明性を保ちます。
環境の変化や様々な理由により、評価項目は定期的に見直していく必要があります。その際には、事業戦略を軸に考えてみてください。将来の組織図を描き、人材戦略を構築してみてください。ステップ3で記載した育成スケジュールが約に立つと思います。
ステップ5: 事業戦略との整合性を検証する
- 評価制度の効果を測定する
- 評価制度が事業戦略の成果(売上成長、顧客満足度の向上、人材定着率の改善など)にどの程度寄与しているかを定量的に測定します。
- 評価制度のKPI(例: 従業員満足度、エンゲージメントスコア、離職率など)を設定し、モニタリングを継続します。
- 事業戦略との連携を再確認する
- 評価制度が事業戦略と一致しているか、定期的に確認します。戦略の変更があれば、評価制度も柔軟に調整します。
ここでのポイントは定性項目がどの程度戦略達成に寄与しているかを測ることです。定性項目部分は、効果がわかりにくいですが、人事ポリシーの観点で非常に重要な役割を担います。