報連相のモヤモヤ解消
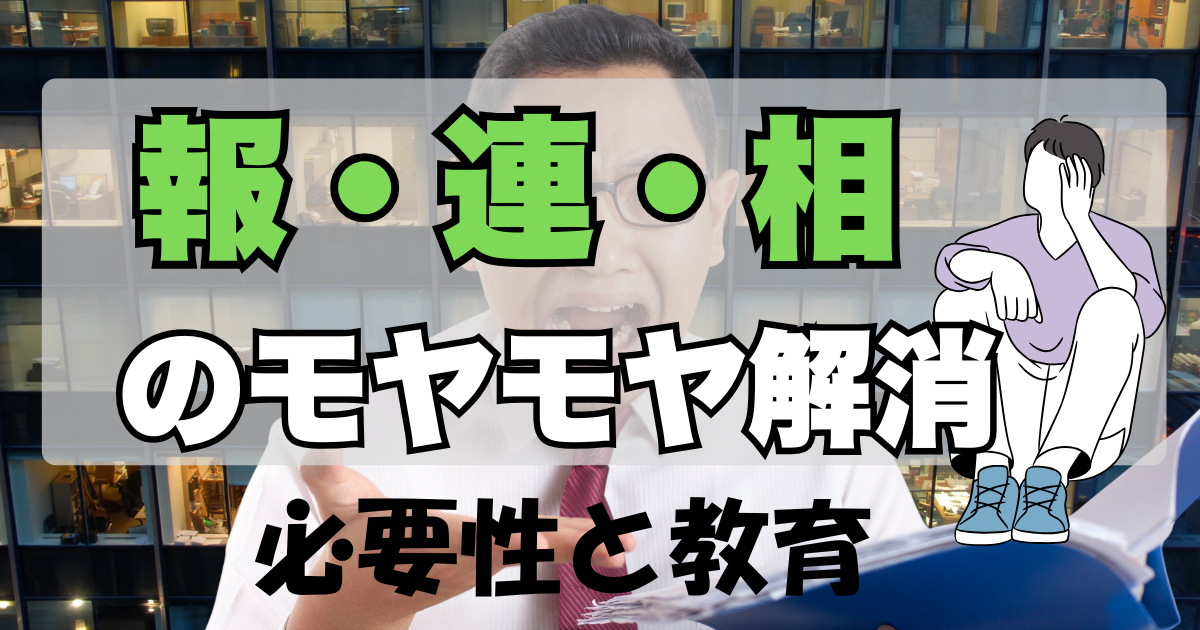
「うちの会社は基本である報連相がうまく出来ていない社員がいる。何度注意しても改善されない」
このような質問を受けることがあります。業務を円滑に行うために報連相が重要だということは言うまでもありませんが、報連相がうまく機能していないことで、人間関係のトラブルにまで発展するケースもあり、場合によっては非常にマネジメントコストがかかります。ここでは、キホンのキである報連相について、社内業務を円滑に行うための報連相について記載します。
そもそも、なぜ報連相が必要なのか。
報連相(報告・連絡・相談)が必要な理由はいくつかありますが、以下のポイントが特に重要です。
1. 情報共有の促進
組織内で情報が適切に共有されることで、各メンバーが共通の理解を持てます。これにより、業務の方向性や優先順位が明確になり、チーム全体が同じゴールに向かって効率的に動くことができます。
2. 問題の早期発見と対応
報告がしっかりと行われることにより、現場で発生した問題や課題が早期に上層部に伝わります。これにより、迅速な対応や解決策を講じることができ、大きな問題に発展する前に対処することが可能です。
3. ミスや誤解の防止
報連相によって、誤解やコミュニケーション不足によるミスを最小限に抑えることができます。特に複雑なプロジェクトや業務では、情報が正確に伝わることで、余計なミスを防ぎ、効率的な作業が可能になります。
4. 組織全体の意思決定支援
必要な情報が適切に流れることで、経営陣や管理職はより正確で情報に基づいた意思決定が可能になります。これにより、組織全体のビジョンや目標が効果的に達成されます。
5. 信頼関係の構築
報連相の実践を通じて、上司と部下、または同僚間での信頼関係が構築されます。透明性のあるコミュニケーションが取れる環境は、職場の士気を高め、職場文化を向上させます。
報連相は、単に日常業務の一部としてだけでなく、組織の健全な運営を支える柱として機能すると言えます。このプロセスがあることで、組織は変化するビジネス環境に柔軟に対応できるのです。
「重要であるにもかかわらず、重要ではないと考える人がいるのはなぜでしょうか?」私は、はじめてこの質問を聞いたときに「そんな風に考える人がいるのか?」と耳を疑いましたが、仕事柄多くの経営者と話をするうちに一定の人数でいることがわかりました。重要ではないと考える方の思考は主に下記のように思えます。
1. 負担感や形式的な作業と感じられる
報連相が形式的な業務ルーチンとして扱われると、形だけの作業になりがちです。特に、報告書や会議が単なる義務になってしまうと、効果的なコミュニケーションとしての価値が理解されにくくなります。
2. 効果が見えにくい
報連相の効果は長期的に現れることが多いため、日常的な業務の中ではその重要性を実感しにくいことがあります。一度に大きな問題を解決するというよりは、小さな問題を未然に防ぐためのプロセスであるため、その価値が見過ごされがちです。
3. 組織文化やリーダーシップの欠如
組織によっては、オープンなコミュニケーション文化が十分に醸成されていない場合があります。リーダーが報連相の重要性を理解し、実践を奨励しない限り、組織全体でその意義が浸透しにくいです。
4. 個人主義や自主性の重視
特に個人主義が強い文化では、単独での業務遂行が重視され、チーム内での情報共有や相談が軽視されることがあります。これが報連相を疎かにする一因となります。
5. 時間的制約
忙しいビジネス環境において、報連相のための時間を確保することが負担と感じられることがあります。緊急の業務に追われ、日常的な報連相を後回しにするケースが多いです。
では、このように考える人もいるという前提で、リーダーはどのようなマネジメントを行えば良いでしょうか。以下を意識してみてください。
1. オープンなコミュニケーション環境の構築
- 定期的なミーティングの実施: 週次や月次で定例会議を設け、報告や相談がしやすい場を提供します。
- オープンドアポリシーの導入: 部下がいつでも相談できるような環境を作り、心理的なハードルを下げます。
2. フィードバックを重視
- ポジティブフィードバックの提供: 報連相をしっかり行ったスタッフに対しては、ポジティブなフィードバックと感謝の気持ちを伝え、行動を奨励します。
- 建設的なフィードバック: 誤解や不足があった場合でも、建設的なコメントをし、改善を促します。
3. 報連相の重要性を教育
- 研修やワークショップの実施: 報連相の重要性やその効果を理解させるための研修やワークショップを定期的に開催します。
- 成功事例の共有: 報連相がうまく機能した具体的な事例を共有し、そのメリットを実感させます。
4. ITツールの活用
- コミュニケーションツールの導入: SlackやMicrosoft Teamsなどのデジタルツールを使って、情報共有をスムーズに行います。
- プロジェクト管理ツールの活用: TrelloやAsanaなどを使用し、進捗状況を可視化して報告を簡易化します。
5. 個別フォローアップ
- 定期的な個別面談: 個々の部下と定期的に一対一の面談を行い、個別の課題や相談事を聞き出す場を提供します。
- キャリア開発支援: 部下の成長やキャリアに関する相談にも応じ、モチベーションを高めるよう努めます。
これらの施策を通じて、リーダーは部下との信頼関係を築き、報連相が円滑に行われる職場環境を作ることができます。また、リーダー自身がその手本を示すことも、部下にとって非常に有効な促進要素となります。
「報連相は出来ているが、解釈にズレが生じてしまうことが多々あり、ロスタイムだと感じる場合がある。そのような場合にはどうすればよいか?」
個人的には報連相の際のフォーマットを作成し、必要な項目を埋めてもらうことを推奨します。上司にとって必要な項目が部下には理解できていない場合もあります。また、その逆もあります。それによるロスタイムをなくすためにフォーマットを作成してみてはいかがでしょうか。フォーマットを作成し運用する場合には以下の点に気を付けてください。
フォーマット運用の際の懸念点
- 柔軟性の欠如
- フォーマットが固定化されていると、状況やニーズの変化に対応しにくくなります。特にイレギュラーな事象や複雑な問題については、フォーマット上に適切な項目がない場合、重要な情報が漏れる可能性があります。
- 形式的な作業に陥る
- フォーマットを埋めること自体が目的化してしまい、内容が形だけのものとなり、報連相の根幹である有意義な情報交換が軽視される危険があります。
- 過度な詳細要求
- 必要以上に詳細な項目を要求すると、報告者に過度な負担をかけ、時間や労力の無駄となります。結果、報告の頻度が減り、本来意図した円滑なコミュニケーションが損なわれる可能性があります。
- 形式への依存
- フォーマットが唯一の報連相手段と捉えられてしまうと、口頭での報告や直接的な相談が減少することがあります。これにより、些細な情報の交換が滞り、重要な気づきや意見がシェアされにくくなることがあります。
対策
- フォーマットにはある程度の自由度を持たせ、状況に応じてカスタマイズできるようにします。
- 定期的にフォーマットを見直し、必要に応じて改定します。
- フォーマットに依存せず、口頭でのコミュニケーションや定期的な直接相談の機会も設けるようにします。
これらの懸念を考慮しながら、フォーマットの導入を進めることが理想的です。フォーマットは共通のガイドラインとして活用しつつ、柔軟な運用を心がけることで、報連相をより効果的にすることができます。