定性評価いらない論争について
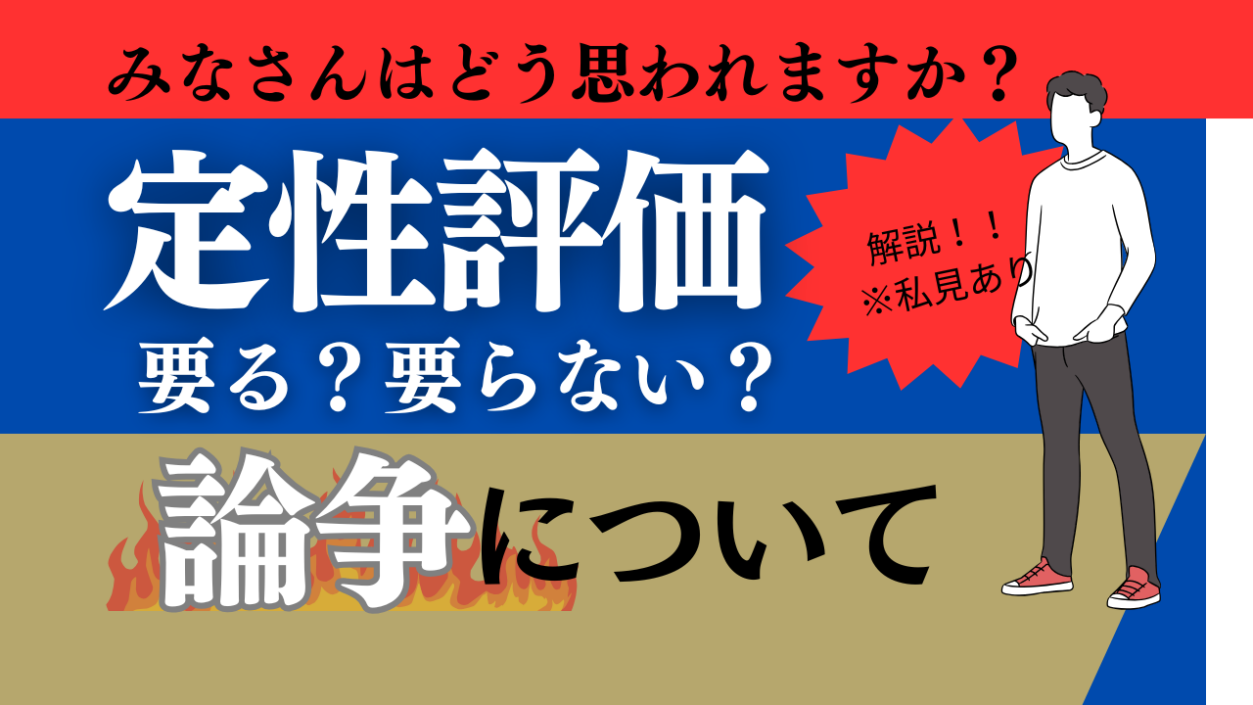
人事評価制度において、「定性評価は必要ない」「全てのことは数値化できる」という風潮がありますが、みなさんはどう思いますか?たとえば、「組織風土を理解し、メンバーを助けることが出来る」という項目に対して、これを4段階くらいに区別して評価していくという制度があった場合に、これに良し悪しを論じるという風潮です。悪いという意見の筆頭格は、「評価者による属人的な評価になってしまう」「基準付けが難しい」という論拠です。この論拠により、全て数値化した方が良いし、定性的なことは評価しないという極論に振れてしまうパターンです。言いたいことはわかりますが、それによる弊害もありそうです。ここでは、意見が分かれる定性評価について話をしていきたいと思います。
人事評価制度における定性評価のメリット、デメリットを見ていきましょう。
メリット:
- 従業員の組織適応能力の把握: 個々の社員の行動や態度、組織への貢献、取り組みに対する姿勢など、数値化が難しい面も含めて評価することが出来る。
- 柔軟性: 設定された数値にあらわれにくい点を考慮することができます。
- フィードバックの質: 主に所属している組織の文化や風土に紐づく基準により設定されるため、その組織で活躍が出来るような建設的なフィードバックを提供しやすく、組織におけるキャリア成長のための具体的な指導ができます。
デメリット:
- 主観性の欠如: 評価者の主観が入りやすいため、公平性を保つのが難しい場合があります。また、部により基準がバラバラで曖昧だと、収拾がつかなくなる場合があります。
- 一貫性の欠如: 会社全体として評価基準が明確ではない場合、一貫性のある評価が困難になります。組織全体での評価基準の統一が必要になります。
- マネジメントコスト: 詳細な評価には時間と労力が必要であり、評価者に負担がかかる可能性があります。また、公平に評価するためには、評価者の評価における知見が必要で評価者の教育が必要です。
- 納得性: 設定された項目に対し、評価者も評価される側にも解釈が存在し、結果に納得しづらい場合があります。その結果、査定結果について異議が申し立てられることがあり、評価者側も納得のいく説明が難しい場合があります。
- 改善点のFBが難しい: 具体的な数値やデータに基づかないため、改善に向けた具体的なアクションプランを提示しにくい可能性があります。
一般的には上記のようなことが言われており、それにより、冒頭のような風潮が起こっているのだと思います。さらには評価者のバイアス(評価者の個人的な経験や価値観)が評価に影響を与える可能性もあるので、偏った評価がされる危険性がありまます。また、評価者が複数人いる場合には、変数が多くなり評価結果に不一致が起こる可能性もあります。
私の意見を述べさせていただくと、定性評価はあった方が良いと思います。「定量評価のみで良い」という根拠については、多くの場合は公平な評価が出来ないという点から発生していると思うのですが、だからと言ってなくしてしまうのは違うのではないかと思っています。組織を運営していくにあたって、数字では測れない部分をきちんと見ていくことは重要です。営業組織であっても、数字を挙げるためにはどういう振る舞いが重要で、何を大事にしないといけないかという規範があった方がよいです。所謂トンマナを揃えるということですが、これは実はかなり重要な概念なのです。
定性部分を評価項目に入れるかという話の前に、「なぜ入れる必要があるのか」から所見を述べたいと思います。人を評価する際には、様々な角度で評価するべきだと考えています。数字だけ強い人がいても人間的に問題がある人を要職につけてしまうと、組織は崩壊してしまう可能性もあります。人間的な部分をどう測るかという観点において、少なくとも測る要素は入れておいた方が良いのではないかと思います。その基準や指針の基となるのは、会社の人事ポリシーになります。人事ポリシーについては、こちらで詳しく記載しておりますので、参考にしてみてください。
人事ポリシーを基とした人材を育成するために、定性部分の効果把握や教育が必要なのですが、どのようすればうまく運用できるでしょうか。大きく分けて二つあります。①評価項目としては入れずに日々のマネジメントで教育していく。②評価項目にして、段階的かつ継続的に観測していく。の二つになるのかと思います。
評価項目としてはいれずに、日々のマネジメントで教育
定性的な部分は、極端なことを言えば、組織における行動規範や与えられた役職に応じた当たり前に出来ていて欲しい部分の基準なので、当たり前の基準を上げていくという趣旨になります。ですので、わざわざ評価するということではなく、上司が日々のマネジメントにより改善していくべき事柄とも捉えられます。考えた方として、評価とマネジメントという枠に分けて教育をしていくという手法です。この場合は、下記の点に気を付けて運用してください。
・定性部分の定義化、明文化をし、出来るだけ解釈に違いが出ないようなものにする。
・評価者による人事ポリシーの深い理解。
・評価者のフィードバック方法の教育
・評価者自身の体現
ポイントとしては、評価者の育成です。言葉にすると簡単ですが、評価者が未熟であると、機能しません。また、複数の評価者によるバラツキがあると、さらに複雑になってしまいます。この方法を選択するのであれば、評価者教育は必須ですし、継続して教育することで、組織文化といえるレベルまで組織に落とし込むことを見据えて教育に取り組んでいきましょう。
評価項目にして、段階的かつ継続的に観測する
評価項目に入れる場合は、デメリットを考慮して設計してください。
・曖昧部分をなくすために、全社共通の基準を設定。評価者により、〇×の解釈がズレないようにする。
・階層により、比重を分けて運用。例:下位層は定性30%上位層は定性10%等。
・定性部分に関しては、行動規範と業務上のルールをバランス良く入れる。
ポイントとしては、定性評価におけるデメリットと言われる部分を取り除いた項目設定と運用ということになります。会社により重要視する事柄が違いますし、設定するにも項目やバランスが重要ですから、評価項目に入れる場合は専門家の助言を得る方が良いと思います。
いずれの方法にせよ、ポイントとなるのは評価者の教育になります。人が人を評価するという行為には責任が伴いますので、経営者は評価する側に然るべき教育を行う責任があります。私が評価者にとって特に重要だと思う教育は次の通りです。
バイアスに関する教育:
内容: 無意識の偏見やバイアス(例:性別、年齢、人種、職種、役職に基づく偏見)について学び、それが評価に与える影響を理解します。評価者が自分のバイアスを理解することが重要です。
評価基準の理解と適用の教育:
内容: 評価基準の解説や具体的な運用方法の理解促進。評価シナリオを用いたワークショップ。評価者が基準を正しく理解し、一貫した方法で適用できるようにすることが目標です。
フィードバックスキルの向上
内容: 質の高いフィードバックを提供するための技術(例:「具体的に」「行動に基づいて」「建設的に」というポイントを押さえたフィードバックの実践)を学ぶトレーニングを実施。評価結果を明確かつ理解しやすい形で伝えられるようにし、受け手の成長を促進するような技術を習得することが目的です。シミュレーションやロールプレイで行います。
事例の共有
内容: 過去の評価における成功事例や失敗事例を分析し、どのような要因が評価結果に影響を与えたのかを検討します。評価制度の必要性を再認識し、具体的な改善点を見つけることが目的です。
定期的なフォローアップセッション
内容: 定期的に評価者同士でフィードバックを共有するセッションを設けます。評価者が自身の評価がどのように受け取られているのかを知り、継続的に改善策を見つけることで、組織全体の評価の一貫性を保つことと、他者評価を得ることが目的です。
メンタリングプログラムの導入:
内容: 経験豊富な評価者が新人管理者に対してメンタリングを行うプログラムを実施します。実践的なノウハウを共有し、全体の評価レベルを引き上げることが目的です。
これらのトレーニングを通じて、評価者は公正で客観的な評価を行うためのスキルを向上させ、評価制度の信頼性を高めることができます。
定性評価は、組織において非常に重要な役割を果たす場合が多く、単に数値だけでは測れない多くの要素を評価するために必須のプロセスだと思います。職場での対人関係の状況を理解する手助けともなり、全体的なパフォーマンスを抽象的に把握することができます。組織の文化や価値観に沿った行動や態度を評価するためには、定性的な要素があった方が良いのではいのでしょうか。マネジメントで改善するか、評価項目として取り入れるのかは企業判断ですが、評価項目として取り入れる場合は、定量評価と定性評価を適切に組み合わせることが重要です。それにより包括的かつ公平な人事評価制度を実現することができます。定性評価は不要ではなく、むしろその有用性を十分に活用することがポイントです。